昨今、SNSで「複数社経営」をアピールするマーケターや自称ビジネスインフルエンサーが増えています。しかし、その実態を見てみると、ホールディングス(持株会社)という戦略的な経営形態ではなく、単に名義を分けた会社を複数設立しているだけのケースがほとんどです。
ホールディングスと適切な法人スキームを活用することで、節税や資金繰りの最適化など大きなメリットがありますが、ただ会社を増やすだけでは逆に無駄が増えるだけです。今回は、ホールディングスの本当のメリットと、「なんちゃって経営」の無意味さについて詳しく解説します。
「複数者経営」アピールが形骸的な理由

SNSで「複数社経営しています!」とアピールしている人の多くが形骸的な理由は、以下に挙げる通りです。端的に申し上げれば、法人を作ること自体が目的化していたりすることが多く、実態の伴わない形骸的な経営であることが多いということです。
実態がない(ペーパーカンパニー)
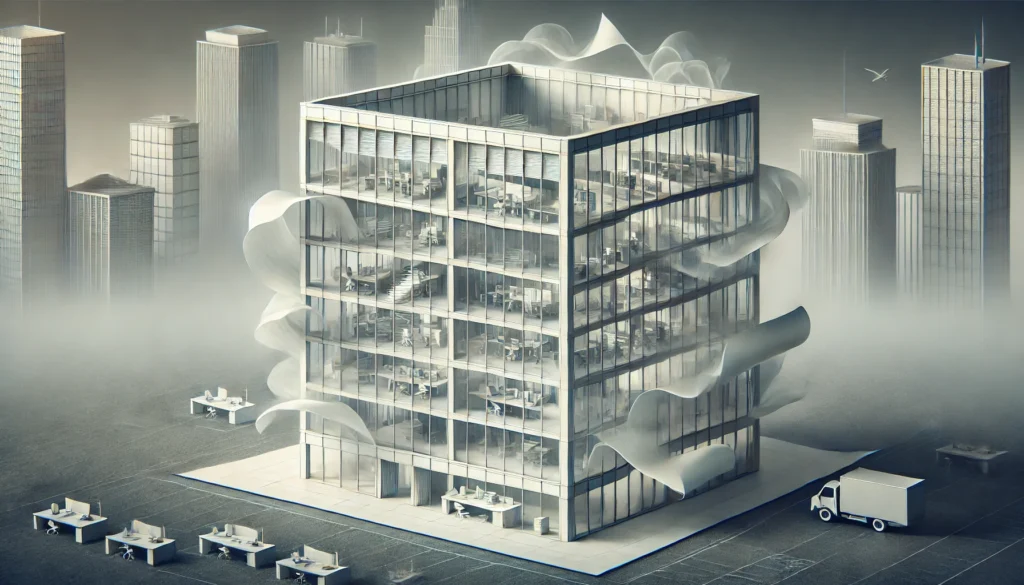
会社を複数作ること自体は非常に簡単で、法的な手続きを踏み、登記費用さえ支払えば誰でも新しい会社を立ち上げることができます。特に近年では、オンラインでの手続きも充実しており、短期間で法人を設立できる仕組みが整っています。しかし、実際に事業として機能している会社ばかりではなく、収益をほとんど上げていない、もしくはまったく売上のない会社も数多く存在します。
こうした会社の中には、法人を持っていること自体に満足し、実態のない「社長ごっこ」に終始しているケースも珍しくありません。名刺には「代表取締役」と堂々と書かれていても、実際には事業の計画も具体的なビジョンもなく、形だけの会社を維持しているだけのことも多いのです。
特に、法人を持っていると社会的信用が得られると考え、個人事業の延長線上でなんとなく法人化する人もいますが、肝心のビジネスモデルが確立されていなければ、単なる肩書き遊びに終わってしまう可能性が高いでしょう。
収益の分散ではなく「見せかけのスケールアップ」

会社を分けることには、本来、事業のリスクを分散し、各事業ごとに適切な運営体制を整えるとともに、最適な税務対策を講じるという合理的な目的があります。たとえば、新規事業を別会社として設立することで、本業への影響を最小限に抑えながらチャレンジできたり、異なる税制のメリットを活用できたりするのです。
しかし、実際にはそのような経営戦略的な意図ではなく、単に「経営者としての凄さを演出するため」に複数の会社を持っている人も少なくありません。会社の実態や事業の中身よりも、名刺やプロフィールに「複数の会社を経営」と記載することで、あたかも大きな実績や影響力があるかのように見せかけることを目的としているケースが多いのが実情です。
事業内容が被っている

例えば、A社では物販事業、B社ではコンサルティング業、C社では広告運用を行っていると表向きには説明しているものの、実際にはそれぞれの会社が独立したビジネスモデルを持っているわけではなく、実態としては、すべて同じ顧客層を対象にした似たようなサービスを提供しており、各社の業務内容も重複していることが多いです。
実際には単一のビジネスの延長線上にある事業を、形だけ分社化しているに過ぎません。そのため、それぞれの会社が独立している意味や必要性はほとんど感じられず、結果的に複数の会社を運営しているように見せることで、事業規模が大きく、多角的に展開しているような印象を与えようとしているケースが多いのが実情です。
役割分担ができていない

多くの場合、その法人は組織としての機能が十分に整っておらず、業務の分担や役割の明確化ができていません。その結果、会社としての体裁はあるものの、実際には経営者自身がほぼすべての業務をこなさなければならない状況に陥ることが多いです。
したがって、新たに法人を増やしたとしても、経営者の負担が軽減されるわけではなく、むしろ管理すべき法人が増えたことで事務作業や責任が増え、より一層の負担を強いられるケースも少なくありません。法人を設立しただけでは、組織としての運営が機能するわけではなく、適切な人員配置や業務の委任がなければ、結局のところ経営者一人にかかる負担は何も変わらないのが現実です。
人を体系的に巻き込めていない

経営者が1人で複数の会社を運営している場合、それは多くの場合、単なる「個人事業の法人化」に過ぎません。本来、複数の企業を経営すると聞くと、大規模な事業や組織を運営しているような印象を受けがちですが、実際には経営チームが存在せず、事業継承の仕組みも整っていないケースがほとんどです。
つまり、会社の数が多いからといって、それが即座に大きなビジネスを展開していることを意味するわけではなく、実態としては1人の個人が複数の法人名義を使い分けながら事業を行っているだけという場合が少なくありません。そのため、企業としての組織力や継続性には乏しく、経営者自身が動けなくなれば、すべての会社の事業が止まってしまうというリスクを抱えているのが実情です。
ホールディングスを活用するメリット
グループ内取引を活用した節税

1つの会社にすべての利益を集中させると、法人税が高くなります。しかし、適切に複数の法人に分散させることで、法人税の負担を抑えることが可能です。
例えば、A社で商品を購入し、B社に貸し出す形でレンタル料を受け取るスキームを構築することで、
- A社の利益を圧縮(仕入れコストとして計上)
- B社はA社に支払うレンタル料を経費化
このように、グループ内取引を活用すれば、法人税の最適化が可能になります。
消費税の節税

A社が課税事業者で仕入れ時の消費税を還付し、B社が免税事業者で消費税を納めない方式を採用することで、消費税負担を減らすこともできます。ただしこちらについては「インボイス制度」の導入により、状況が変わってきていますので、情報収集の際は「インボイス制度に対応した術かどうか」が要です。
ちなみに、消費税の課税対象となる売上を分散することで、1,000万円以下の法人を維持することも可能ではありますが、特に物販ビジネスの融資の際、売上を低く見積もることは一概にメリットとも言えませんのでご留意下さい。
「1法人+個人事業主」の汎用性

個人の所得税を低く抑えるために、複数の法人から適正な範囲で役員報酬を受け取ることも可能です。1社で高額の報酬を取ると高税率が適用されますが、複数の会社から分散して受け取れば、所得税率の低い範囲で調整できます。
ただし、そもそもホールディング化するほどの規模ではない場合が多いかと存じますので、一般的には持ち株会社ではなく「1法人+1個人事業主」の形態の方が汎用性あるかと存じます。法人の役員報酬は「社会保険料を享受できる下限」ギリギリに設定し、別途、個人事業主として上手くやりくりするという方法です。詳細については、専門家である税理士さんに問い合わせるのが最善手です。
ただ会社を増やすだけでは節税にならない

法人を増やせば、単純に登記費用、会計・税務処理コスト、銀行手数料などが増えるだけです。また、法人税は売上が少なくても最低限の均等割が発生するため、利益が出ていない会社でも維持費がかかります。
戦略的に設計されていない「なんちゃって複数社経営」は、税金が減るどころか、単なるコストの増大につながるだけです。
会社の数を増やすことに意味はない

本当に経営がうまくいっているなら、会社の数を増やすよりも、1社の利益を最大化し、ホールディングス化するなどの合理的なスキームを構築する方が、税制メリットも資金繰りの安定も得られます。
しかし、多くのSNSマーケターは「複数社経営=成功者アピール」としか考えておらず、実際には何の意味もない会社を増やしているだけです。
実態のない法人経営はリスク
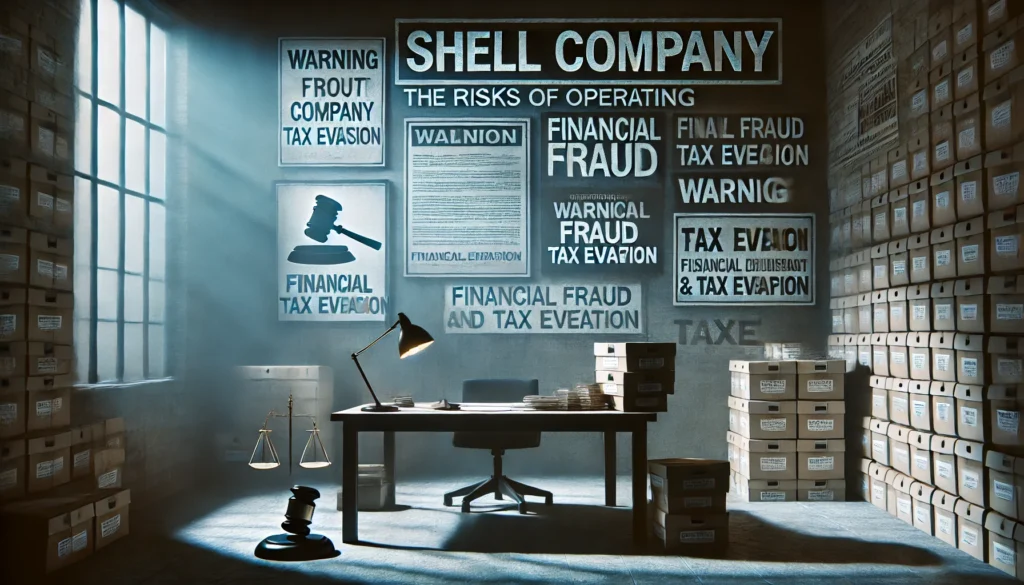
銀行融資を受けようとしても、実態のない会社が複数あるだけでは、金融機関からの評価は低くなります。また、法人の運営実態がないと、税務調査が入った際に「租税回避目的」とみなされるリスクもあります。
本当に経営を考えるならホールディングス化もあり

本気で経営を考えるなら、
- 法人税や消費税の最適化を考えたスキームを構築する
- 収益の分散を考慮しつつ、無駄な法人を作らない
- 資金繰りの安定を優先する
といった視点が必要です。

ただ法人を増やすのではなく、ホールディングス化や法人間取引を適切に設計し、資金と税務の両方を最適化することが、本当の意味での「賢い経営」です。「俺は複数社経営している」とアピールすることに意味はありません。重要なのは、その法人をどう活用し、経営をどう最適化するかです。
まとめ

✅ ホールディングスは、法人税・消費税の最適化や資金繰りの安定化に有効
✅ 単に会社を増やすだけでは、税制メリットはなく、逆にコストが増える
✅ SNSで「複数社経営」をアピールするマーケターの多くは、戦略的な法人運営をしていない
✅ 本当に経営を考えるなら、ホールディングス化を視野に入れるべき
法人経営は、見せかけではなく、実際の資金や税制の最適化を考えてこそ意味があります。経営を学ぶなら、SNSマーケターの「なんちゃって経営」を真似するのではなく、実践的なスキームを研究し、ビジネスの本質を押さえるべきです。


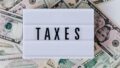
コメント